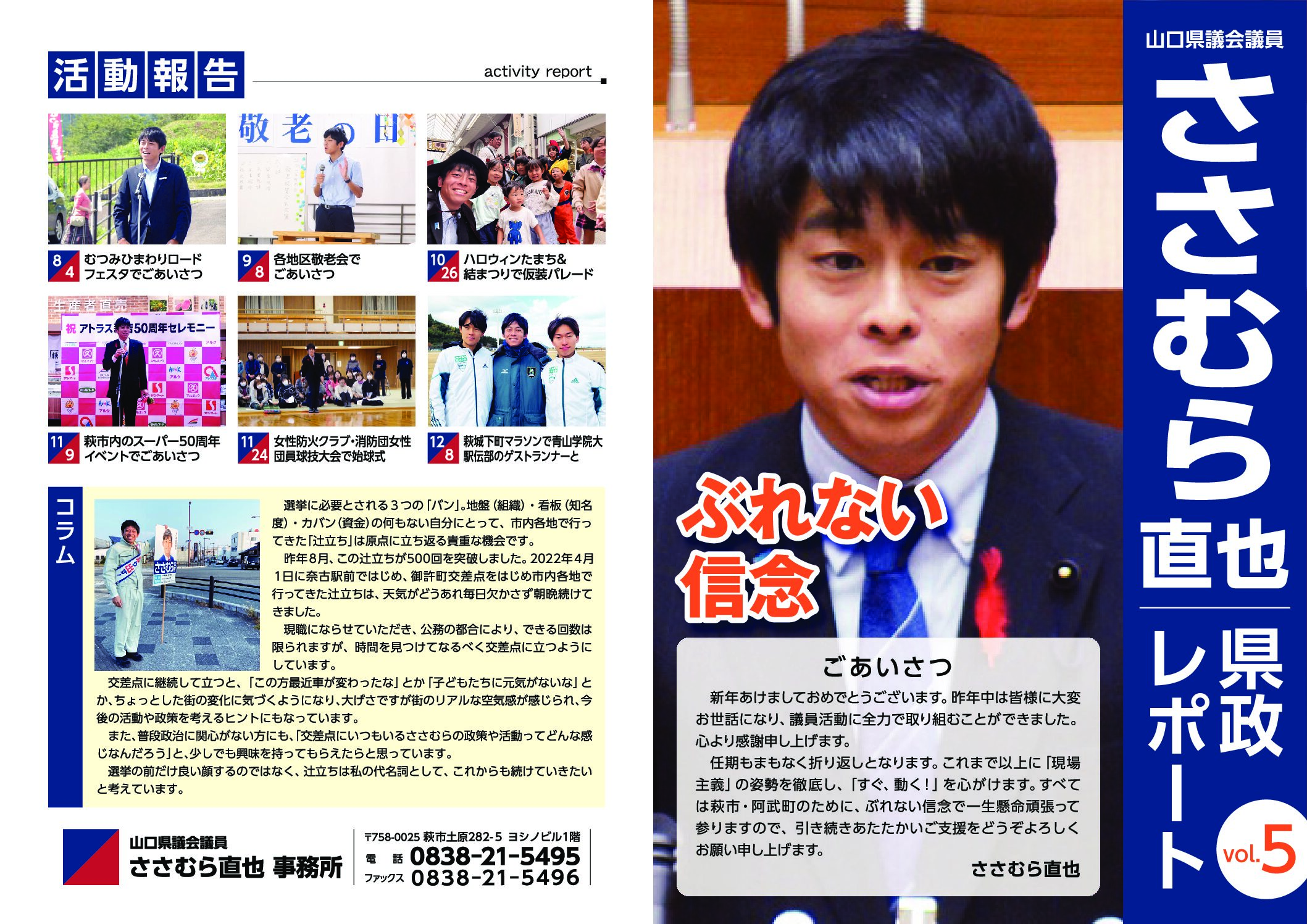県議会一般質問⑤「災害への備えについて」

【Q】
私は8月に、自民党青年部・青年局の海外視察研修に参加し、全国の同年代議員たちとともに昨年4月にマグニチュード7・7の大地震が発生した台湾東部の花蓮県を訪問しました。花蓮市長らから被災当時の状況や復旧状況などについて説明を受け、「人的、物的に大変な被害が発生したが観光地として大半は復旧を終えておりぜひ日本の方にも安全・安心な場所であることをPRしてほしい」とのことでした。実際、ところどころ倒壊した建物の残骸はみられたものの復旧・復興は相当程度進んでおり、海に面した穏やかな観光地であるとの印象を受けました。
しばしば、災害対応を台湾に学べと言われます。花蓮における今回の地震の対応をみると、発災直後に建物のトリアージを行い、周囲に危険を及ぼしうる建物についてすぐに専門家を呼び、解体に着手しました。また、政府・県・市などの情報はすべてクラウドで共有し、関係機関が普段から入力訓練や情報共有の訓練をしているとのことでした。これにより、問い合わせや会議の手間が省け、迅速に必要な対応を取ることができたとのことです。
県が主導した対応としては、住宅を中心とした建物の再建支援があげられます。花蓮における地震で被害が拡大した要因として、先住民も多く被災家屋の相当数が耐震基準を満たしていなかったことがあげられます。これにより政府の再建支援を得にくい状況で、県が独自支援を検討し、政府にはさらなる再建支援の増額を要請しました。また、被災者相談の窓口は本来、市の役割でしたが県が主に対応したということでした。
また、慈善団体、民間団体、企業の主導ですが、避難所においては、避難者がプライバシーを保護し、できるだけストレスを低減した環境で過ごせるよう、簡単に組み立てられるパーティションを各避難所にあらかじめ用意し、迅速に展開されました。県と市は平時からこうした団体や企業と連携し、災害に備え検討と訓練を繰り返していたといいます。
我が県を取り巻く状況をみると、今年8月に宮崎県東部の日向灘を震源とするマグニチュード7・1の地震が発生し、その後、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されたのは記憶に新しいところです。本県は比較的地震による被害は少ないとされていますが、過去には大規模地震による被害があったとの記録もあります。実際、本県の南海トラフ地震による被害想定では、最大震度6強、死者614人、負傷者1477人とされています。南海トラフ地震は30年以内に70~80%の確立で発生するとされ、現実問題として発生を抑えることができない以上、発生を前提とした対策を講じる必要があります。1月には能登半島地震も発生し、災害への脅威や備えの必要性を県民誰もが身近な問題として感じる中、行政として災害にどう備え、対応するか、3点お尋ねします。
1点目は建築物の耐震化について、本県は令和4年7月に改定した「山口県耐震改修計画に」に基づき、住宅や多数の者が利用する建築物等について、目標を定めて耐震化を促していますが、その状況は全国平均と比べ下回っていますが、どのように今後耐震化を進めて人命や財産を守っていくのか。
2点目に、発災時の円滑な情報共有、迅速な対応に向けて行政機関の情報共有のあり方についてどう考えられているか。3点目、避難所におけるプライバシーの保護に資するパーティションの導入検討について、県のご所見をお伺いいたします。
【A】
建築物の耐震化についてお答えします。
県では、地震による建築物の被害及びこれに起因する人命や財産の損失を未然に防止するため、お示しの「山口県耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震改修を総合的かつ計画的に進めているところです。
こうした中、熊本地震や能登半島地震では、現行の耐震基準を満足していない多くの家屋が倒壊するなど甚大な被害が発生し、住宅や多数の者が利用する建築物等の耐震化の重要性が一層高まっています。
住宅については、これまで、市町と連携し、所有者に対し耐震化の必要性をはじめ、木造住宅の無料耐震診断や耐震改修などに対する補助制度を周知するとともに、耐震診断等に携わる技術者向けの講習会を実施するなど、耐震化の促進に向けた取組を進めてきたところです。
今後、耐震化をより一層進めるため、さらなる所有者の意識醸成に向けて、様々な広報媒体を活用した普及啓発に取り組んでまいります。
加えて、工事費用が高いことを理由に耐震改修工事の実施が困難とされる場合が多く、近年注目され始めた比較的安価な工法の普及が耐震化の促進につながることから、改修事例について情報提供するとともに、それを施工する技術者を養成するなどの取組を強化してまいります。
また、多数の者が利用する建築物等のうち、大規模なホテルや病院等の耐震診断義務付け対象建築物については、市町と協調した補助制度を周知するとともに、毎年度、全ての所有者等に対して、耐震化に取り組むよう働き掛けてきたところであり、引き続き、個別訪問の実施など直接的なアプローチを行ってまいります。
県としては、県民の安心・安全を確保するため、市町と連携し、住宅や多数の者が利用する建築物等の耐震化の促進に積極的に取り組んでまいります。
災害時における行政機関の円滑な情報共有のあり方についてです。
災害発生時の様々な課題に臨機応変に対応するためには、行政機関の円滑な情報共有が重要であることから、県では、平素から県や市町、関係機関等との連携体制を構築し、防災訓練等を通じてその強化を図っています。
具体的には、県の総合防災情報ネットワークやクラウドを活用し、行政機関のみならず、防災関係機関も含めて、平時には各種計画やマニュアル等を、発災時には被害状況やその対応等の情報を迅速に共有しているところです。
今後は、避難者への支援をより迅速かつ円滑に行うため、県と被災市町とが連携し、各市町の避難者情報を一元的に管理する全市町共通のシステムの導入を検討することとしており、システムの更なる活用を通じ、市町との情報連携体制を強化してまいります。
次に、避難所における生活環境の改善についてです。
被災者が一定期間滞在する場所である避難所においては、プライバシーも含め、良好な生活環境の確保が重要であることから、県では、「避難所運営マニュアル策定のための基本指針」の中で、市町に対し、必要な資機材の備蓄等を促しています。
お示しのパーティションなど、避難所環境の改善に必要な資機材の整備を進めるためには、国の財政支援が必要なことから、県議会とも連携し、国に要望を行ったところです。
さらに、国の総合経済対策において「避難所環境の抜本的改善」に取り組むこととされたことから、県としてもこれに呼応し、国の支援メニューも活用しながら、市町における避難所の環境整備を促進していくこととしています。
県としては、今後とも、市町や関係機関等と緊密に連携しながら、災害対応力の強化と避難所の良好な生活環境の確保に取り組んでまいります。